少子高齢化による労働人口減少がもたらす人手不足が深刻となる中、生成AIの台頭によって業務効率化が飛躍的に進むなど、我が国のビジネスを取り巻く環境は日々変化を続けています。上記のような状況の中、DXによるビッグデータの活用・新しいビジネススキームの構築こそが、これからの企業の競争優位性を高める重要な鍵となっていくでしょう。本記事では、こうした諸課題を乗り越える未来へ向けた、企業によるDX戦略の意義や、具体的な進め方、国家による政策や取り組みについて詳細に解説していきます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略とは
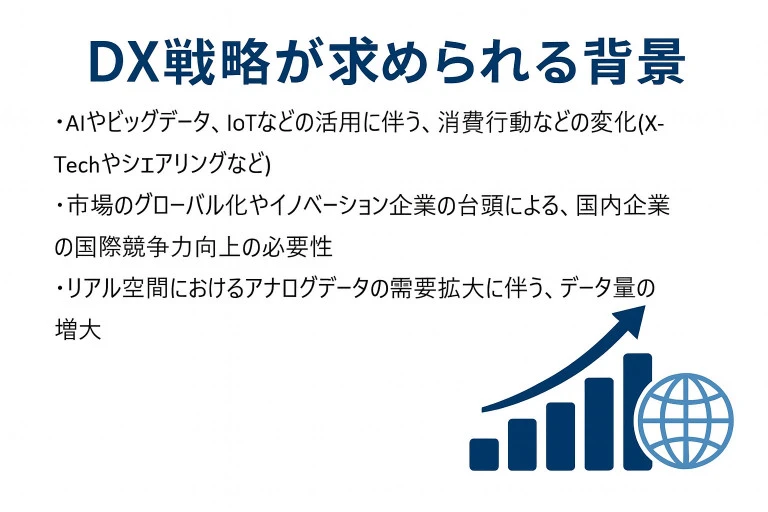
コロナ禍以降、DXやDX戦略という言葉を聞くことが増えてきた一方で、そもそもDXとはなんぞや?DX戦略とは何をすることなのか?と疑問に思っている方も少なくないのではないでしょうか。ここでは、そもそもDX戦略とは何なのか、今後重要視される理由を含めて解説します。
DX戦略の定義
DXとは、「デジタルトランスフォーメーション」の略で、経済産業省の『デジタルガバナンスコード3.0』では、“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”と定義されています。
DX戦略とはすなわち、デジタル技術を活用しDXを適切に策定・実行することにより、企業のビジネスモデルや組織・業務プロセスを根本的に大きく変える取り組みなのです。
よく誤解されますが、DXは、単なるITの導入や短期的なコスト削減・業務効率化を目指す取り組み(=デジタル化)ではありません。DXは「新しいビジネスの仕組みを構築して競争力を高めること」に主眼が置かれており、中長期的な企業価値の向上を目的とします。
DX戦略が今後重要視される理由
特にポスト・コロナの現在において、DX戦略の重要性は非常に大きなものとなっています。リモートワークなど場所にとらわれない多様な働き方への対応、業務効率化や自動化など「デジタル化」も急務ではありますが、その枠を超えたDX戦略が求められる背景として、主なものは以下の通りです。
・AIやビッグデータ、IoTなどの活用に伴う、消費行動等の変化(X-Techやシェアリングなど)
・市場のグローバル化やイノベーション企業の台頭による、国内企業の国際競争力向上の必要性
・リアル空間におけるアナログデータの需要拡大に伴う、データ量の増大
これらは毎年のように激変するIT社会の中心に位置する要素といえます。こうした荒波に日本企業が立ち向かっていくためにも、DXを通したイノベーション、すなわち組織やビジネスモデルの抜本的な改革が必要です。
また、特に日本国内において重要な観点として、地方創生におけるDX化の推進が挙げられるでしょう。大都市圏への人口集中に伴う地方の衰退を防ぐため、地域社会・地方経済の活性化の推進のために、「デジタル・新技術の徹底活用」を主軸にした、地域課題の解決の手段としてのDX戦略に期待が高まっています。
東京への一極集中、超高齢化による地方人口の減少といった日本で特に顕著な課題の解決にも、DX戦略は重要な位置を占めているのです。
DX戦略の立て方と進め方

DX戦略において重要なのは、中長期的な企業価値向上に寄与する変革です。そうしたゴールに向けてDX戦略を立てる上では、現場から経営層まで全社的に取り組みつつ、経営戦略と相反しないシームレスなDX戦略を立案・実行していく必要があります。ここでは、DX戦略が単なる技術導入で終わらないために、どのようなことを考えて戦略を立てて進めるべきなのか、具体的なプロセスを解説していきます。
1.DX戦略・経営戦略が互いに整合するビジョンを設計する
DX戦略を策定するにあたっては、まずは経営層のDXへの理解が不可欠です。
DX戦略において重要なのは、IT技術導入それ自体ではなく、技術導入に合わせた組織変革や業務プロセスの変革です。個々の業務レベルを超え横断的に浸透している既存のシステムを変えていくためには、企業全体レベルでの意思決定が必要となります。
具体的には、経営課題を解決していくためのデジタル活用と、デジタル活用を通して新たな経営戦略を創出するという、2つの観点からDX戦略を組み立てていくのが肝要です。このように経営層の意思決定の元で相互補完的なベースを作ることで、DX戦略と経営戦略がより強固に結びつくことが期待されます。
DX戦略を進めていく上で目指すべき方向性を失わないよう、経営層が思い描く経営戦略と、全社的に取り組むDX戦略が互いに整合するビジョンを策定することが、DX戦略の一丁目一番地であり、大前提の第一歩といえるでしょう。
2.経営層から現場まで全社的にDX戦略にコミットする方針を立てる
DX戦略の成否は、「全社的に取り組むことができるか」にかかっています。
DX戦略とは得てして抽象的なものになりがちなため、経営層が単にビジョンや戦略を示すだけでは、現場とのギャップや軋轢によって結局DXが形骸化してしまうリスクがあります。
DX戦略を着実かつスムーズに進めていくためには、全社横断的に責任や意思決定権を持つ経営層が、DX戦略への強いコミットメントを持ち、取り組みを先導していく姿勢が大切なのです。
具体的には、行動指針を明確にした上で、DX戦略に適した人材の育成や採用を実施し、併せて先行設備投資を行うなど、現場の体制を整えます。その上で、各部門や現場から出た課題や不都合などの洗い出しや意識調査などのヒアリングを行い、適宜内容を見直していくことも重要です。
このように、トップダウンとボトムアップの両輪で変革を進めていくことが、DX戦略の最適な進め方です。従来デジタルに関わりが薄かったような部門も積極的に巻き込み、部門ごとの事情に合った形での変革が進められるよう、経営層と現場双方にとって風通しのいい体制を構築していきましょう。
3.DX戦略策定・実行の4ステップ
DX戦略は単発の取り組みではなく、全社的な戦略として立案することが求められます。基本的なステップは以下の通りです。このステップを繰り返すことによって、PDCAサイクルを回すように企業競争力を高める経営資源の獲得、活用へと繋げていきましょう。
- ビジョン(経営ビジョンとDX戦略)の策定:DX戦略に基づいた意思決定を行う。DX戦略のためのロードマップ、タスクリストなどの策定を行うことで、DX戦略の方向性を決めるとともに、DXを通じて企業が社会に提供する価値を明確にする。
- 全社的なDX戦略への準備:新規DX戦略チームの立ち上げ、投資の採算やツール導入の試算、既存インフラや既存業務の棚卸し、部門ごとの課題と改善余地の洗い出し、現場と経営層の連携構築など。
- DXの推進・実現・拡大:全社横断でのDX導入とツールの活用、新たに得られた社内データの分析と活用を通して新たな価値創出をはかり、大胆な投資や意思決定によって顧客へ新たな価値を提供する。
- 成果評価とブラッシュアップ:DX戦略の効果を測定する指標(例:業務自動化率、CO₂削減量、売上貢献額)と実際に得られた成果を評価検証し、更なる見直し、ブラッシュアップを実施する。
DX戦略のメリット

生産性向上や組織運営の最適化、将来的な企業価値の向上に設定し、中長期的に取り組むことでこそ、DX戦略の本当のメリットが得られます。
ここでは、企業がDX戦略を推進することで得られる本質的なメリットを紹介します。
生産性の向上
DXはデジタル化によって業務プロセスの見直しや最適化をも図る施策であり、業務全体の生産性向上にもつながっています。具体的には、バックオフィス業務におけるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入やクラウド環境でのデータ活用、近年ではAIの活用などが代表的です。
経営判断の迅速化・高精度化
DXによる社内データの可視化や、KPI達成率など目標設定の見える化によって、デジタルを活用した経営判断も可能になります。また、DXをAIと連携させることで、より迅速で高精度な経営判断を行うこともできるでしょう。
顧客提供価値・収益等の向上
既存ビジネスの深化、新規事業の創出などによる顧客提供価値の向上も、DXの重要なメリットです。既存ビジネスを中心とした業務最適化による収益等の向上に加え、新たなバリューやイノベーションにつながる新規事業の創出などの成果が得られます。
顧客体験価値(CX)の向上
DXによって既存ビジネスをデジタル化することで、多様な形でのサービス展開が可能になります。例えばオンラインと対面の選択など、顧客の好みによって最適なサービスの提供が可能となることで、顧客はより快適にサービスを利用できます。これが「顧客体験価値(CX)の向上」です。
DXによって顧客行動を可視化し、パーソナライズされたサービスと、サービスを必要とする顧客とのマッチングが最適なタイミングで実施できます。
国境や産業を跨いだ広範なデータ連携による付加価値の向上
DXでは、業界を跨いでデータを共有することも重要です。データを活用した広範な連携は、GXや地域インフラなど新たな領域での活用も可能になり、企業の競争優位性を超えた社会的課題の解決、社や業界を超えた社会的な価値の創出という大きな成果が期待できます。
サイバーセキュリティ強化によるインシデントリスクや損失の縮小
先に触れた広範なデータ連携においては、サイバーセキュリティは「必要不可欠な投資」です。
DX戦略を進める際には、必然的にサイバーセキュリティリスクを把握・評価し対策する工程が挟まります。DXとサイバーセキュリティ強化は一体のものなので、DXを進めることで結果的にサイバーセキュリティ対策を実施できるのです。
すなわち、DX戦略を進めることにより、サイバーセキュリティリスクを最小化でき、企業の信頼性担保にも繋がります。
DX戦略を進める上での注意点

DX戦略を単なる技術導入で終わらせないためには、DXを全社的な取り組みとして進めなければなりません。ここでは、DX戦略を全社的取り組みとして進めていく上での注意点や、意識するべきポイントについて整理して解説していきます。
単発の短期的な取り組みで終わらないこと
DX戦略は企業の組織変革や業務変革、ひいてはビジネスモデルの変革や新規事業の創出にもつながる、企業にとってのコア戦略となります。業務変革による成果を見定める上でも、サービスをブラッシュアップしていくためにも、単発や短期で終わらせず、時間をかけて顧客や市場のリアクションや変化に対応しながら継続していく必要があるでしょう。企業の組織全体を変革することで新たな価値を創出するために、DXはあくまでも中長期的な戦略として扱うことが大切なのです。
段階的に実施していくこと
DX戦略の策定やビジョンの設計などの意思決定は、経営層による全社的な判断と先導が必要になりますが、実際に進めていく上では各部門とのきめ細かな連携と調整が必須となります。DX戦略による大規模なシステム変更や業務改革を一気に進めてしまうと、現場での混乱やトラブルの頻発、ひいては経営層への不信感をも招き、本末転倒です。将来的に大きな変革を行うつもりだからこそ、DX戦略を実行していく際には、小規模なプロジェクトから始めて、徐々に段階を踏んで規模を大きくしていくのが最適です。
経営層が強いリーダーシップを発揮すること
DX戦略の実行は経営戦略にも大きく関わってくるものです。技術導入ありき・IT部門に丸投げなど、ビジョンや仕組み化を明確にしないままDXの指示だけを行っても、現場の抵抗に遭ったり、結局目的が不明確で進まなくなったりして失敗してしまうでしょう。
そのため、経営層によるDXへの明確なコミットメント、具体的には経営権限を利用した組織整備が必要になっていくのです。DXを行っていくために適切な人材や予算の配分、個々のプロジェクトの管理から、人事評価の見直しまで、DXに最適化された組織的な仕組みの整備を経営側の権限において徹底することで、DXへのコミットメントを高め、全社的取り組みがスムーズに進むことが期待されます。
日本企業におけるDXの現状と課題

2025年現在、日本国内では大企業を中心にDXへの取り組みが進んでいます。IPAが取りまとめた『DX動向2025』によれば、1001人以上の従業員を持つ企業においては何らかのDXを実施している割合が96.1%となっていて、これは米国、ドイツよりも高い数値です。しかしながら、日本企業におけるDXにはまだまだ課題が山積しています。
まずは、中小企業のDXが進んでいないこと。100人以下の中小企業の場合、何らかのDX を実施している割合は46.8%と1001人以上の企業と比べて2倍以上の差が開いています。
そして、日本のDXの成果が「コスト削減・効率化」に偏重していること。本来、DXのゴールは新規ビジネス創出やビジネスモデルの変革であり、米国やドイツの企業ではこうした側面で成果が出ていますが、日本の企業はなかなか成果を出せずにいます。本来のDXが進んでおらず、業務効率化やコスト削減に留まっているのは、日本の大きな課題といえるでしょう。本来あるべき全社的な視点よりも、個別の業務プロセスの改善すなわち「部分最適」に留まる傾向がある点も課題です。
またDX戦略における部門・組織間の連携が弱く、ステークホルダーへの共有が進んでいない点も指摘されています。さらにはDXの手前の段階であるデジタル化の遅れに関しても課題があり、令和7年度版の『情報通信白書』によれば、「DXの役割分担や範囲が不明確」「明確な目的・目標が定まっていない」などDXにおけるビジョンの不明確さや、レガシーシステムやアナログに偏った企業風土の障壁、リソース不足も課題として指摘されています。
国内のDX戦略に関する政策動向

DXは、日本においては企業のみならず国家ぐるみで重要視されており、政府や自治体からも様々な資料やレポートが公開され、DXを支援・推進する政策が進められています。ここでは、日本国内におけるDX戦略に関する政策動向について紹介していきます。
DX戦略は国家的課題として重要視されている
日本国政府はDXを「デジタル社会の実現に向けた重点計画」のうちの重要な課題と位置付けており、デジタル庁を中心にDX推進のためのガイドラインやロードマップ、成果レポートなど情報を積極的に提示するとともに、DX支援のための各種政策・補助金事業を整備しています。
また、社会全体のデジタル化の司令塔機能の強化にも取り組んでおり、国をあげてDXを推進していく体制を整えています。たとえば、「情報処理の促進に関する法律」に基づくDX認定制度や、DXに取り組む上場企業を対象とした「DX銘柄」の選定と公表、中堅・中小企業等を対象としたDX優良事例の選定制度「DXセレクション」などです。
DX戦略を実施する上での喫緊の課題としては、特に国内企業のデジタル基盤、特にAIフレンドリーなデジタルの利用環境・インフラ整備、データセンター整備の加速、データ連携・利活用の促進、サイバーセキュリティの確保などが挙げられます。
参考:デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画』
特に日本においてはデジタル化の遅れが指摘されており、今後もさらなるDX推進が求められていくでしょう。
GXとの同時推進が望まれている

近年、DXの進展や生成AIの台頭による電力需要の急激な増大が課題です。政府では、脱炭素社会の実現のための施策であるGX(グリーントランスフォーメーション)による国内での脱炭素電力の確保を、「DX成否の鍵」と位置付けています。
参考:内閣官房GX実行推進室『GXをめぐる情勢と今後の取組について』
GXは、「グリーントランスフォーメーション」の略で、経済産業省による定義では「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指す」施策のことです。簡単に言えば、脱炭素化や持続可能性の向上によって企業価値を高める取り組みを指します。
DXの進展に伴う電力供給の確保にGXが役立つだけでなく、DX推進に寄与するサプライチェーンの安定化・高度化がGX施策においてもさらなる競争力向上につながることから、DXとGXを組み合わせて活用すべきとしており、DXとGXの同時推進実現が広く望まれています。 DXによるデータ量増大に伴う電力確保や競争力向上においてGXが必要であるのと同様に、GXの実行にもDXが必要です。
政府によるDX・GX推進への取り組みが進んでいる
2025年現在、政府によるDX・GX推進に向けた政策(支援策・先行投資推進策)については、国家主導で長期的に複数年度に渡って、企業や自治体などと密に連携をとりながら実行に移されています。
たとえば、建設分野における「建築GX・DX推進事業」では、DXによるBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)※1の普及と拡大、GXによる建築物のLCCO₂(ライフサイクルカーボンCO₂)※2削減の推進の双方を一体的かつ総合的に支援することで、環境負荷の削減と生産性向上を同時に実現する政策が実行されています。
※1 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング):コンピューター上で建物の3次元モデルを作成し、設計・施工・維持管理といった建物のライフサイクル全体にわたる情報を一元的に管理・活用する仕組み。
※2 LCCO₂(ライフサイクルカーボンCO₂):製品や建築物が、原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で排出するCO₂の総量。
また、他にも「GX経済移行債を活用した投資推進策」における様々な事業に対して、国家予算を配分しています。
その1つとして今後注目するべきは、コンビナート再生型の産業集積の形成や、脱炭素型の新規産業団地整備を、国家戦略特区制度を活用するなど自治体と連携して取り組むGX産業立地政策です。
この政策は、内需縮小に応じて生じたコンビナートの空きスペースを活用して、データ量増大に備えるデータセンターの立地や、AI・ロボティクスを活用した最先端産業の立地を促進するもの。これは、「GX2040ビジョン」でも示された「規制と支援一体型の取組」のひとつであり、「地方創生2.0」構想の柱として、今後も進められる予定です。
参考:経済産業省『GX2040ビジョン ~脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂~』
「GX推進に向けたDX戦略」は具体的にどう進めるのか?

以上のように、G XとDXは相互に密接な関係にあり、双方を同時に進めていくことが重要です。脱炭素社会における企業価値の向上へ着実に繋げていくために、GX推進に向けたDX戦略はどのように進めていくべきなのでしょうか。以下に、GX推進に向けたDX戦略に必要な代表的な施策について解説していきます。
脱炭素による電力供給体制の確保(省エネ・再エネ)
GX推進に向けたDX戦略の代表的なものは、脱炭素による電力供給体制の確保です。
将来的な電力消費拡大に備えるための施策としては、DXによる電力消費量の可視化と最適化が考えられます。これは、IoTセンサーやスマートメーターを用いて拠点別のエネルギー消費量をモニタリングし、得られたデータをEMS(エネルギーマネジメントシステム)により一元管理することで、エネルギー効率の最適化を図るものです。これにより大幅な電力コストの削減が期待できます。
また、政府では、「データセンターの大規模集積型」のGX産業立地政策も策定しています。今後の日本の産業における必須インフラであるデータセンターを特定の地域に集積することで、より効率的な電力・通信のインフラ整備を行うものです。脱炭素電源は地域偏在性があることもあり、クリーンエネルギーの活用においても特定の地域に企業を集積する取り組みも今後進んでいくでしょう。
なお、「GX戦略地域」制度※3の活用による、「脱炭素電源を活用した産業団地等の整備」も、今後の取り組みが期待されています。
※3「GX戦略地域」制度:政府が推進する「GX(グリーントランスフォーメーション)」の中核拠点として、官民が連携し特定の地域を重点的に支援する制度。
DXによりサプライチェーン全体を可視化・最適化
DXを通したサプライチェーン全体の可視化・最適化などの施策も重要です。
たとえば、ブロックチェーン技術などを活用することで製造過程のトレーサビリティを確保し、CO₂排出量(Scope1〜3)を正確に把握することにより、脱炭素に向けた指標を可視化します。そうした指標を用いて顧客や取引先との連携をすることで、サプライチェーン全体での環境負荷の最適化を行っていく、という具合です。
実際、グローバル企業はscope3のCO₂排出量削減に向け、サプライヤーにも環境要件の厳格化を求めるなど、産業全体レベルでのGX連携を行うための取り組みを実施しています。たとえば、マイクロソフトでは「2030年までにMicrosoft向け製造工程で使用する電力を100%炭素フリー電力にするよう義務付け」るなど、サプライヤーに向けて広く脱炭素を呼びかけています。
出典:内閣官房GX実行推進室『GXをめぐる情勢と今後の取組について』
DX・GXを前提としたデータ基盤やITインフラの強化
DX・GXの根幹となるデータ基盤やITインフラの強化も非常に重要です。これは、先に少し触れたGX産業立地策にも大きく関係します。
企業のデータ基盤を担うデータセンターは東京や大阪に集中していますが、いざこうした大都市で大きな災害が起きた場合を想定すれば、この状況はリスク管理の面でもレジリエンスの観点からも非常に危険といえます。そのため、データセンターの地域分散化は、データ基盤の強化において急務といえるでしょう。
また、電力・通信インフラの効率的な連携(ワット・ビット連携)も、DXを加速させていく上で非常に重要な施策です。電力・通信インフラ設置に相応しい地域への立地を促進することで、DXとGXをより効果的に推進できる状況が期待されます。
DX戦略は全社的な取り組みが重要

DX戦略においては、トップダウン・ボトムアップの両輪を軸とした、全社的な取り組みが重要になります。
まずは業務効率化・自動化・コスト削減などデジタル化を中心とした小規模なプロジェクトから導入検証を行い、徐々に全社横断的な業務プロセスの変革へと拡大していくようにすると、現場とのギャップも少なく、着実にDX戦略を進めることができるでしょう。
自社の経営課題解決だけでなく、産業全体の課題解決やイノベーション創出へと繋げていくことも、将来的な企業価値の向上、国際競争力の向上を目指すうえで大切なことです。
政府も企業に向けた色々なDX支援策や諸制度を策定しつつ、様々な投資やバックアップを行っています。これを機に、御社でもDX戦略に取り組んでみてはいかがでしょうか。
また、DX×GXの観点で、今後特に重要になってくるのが、データセンターの設置や電力・インフラ整備のための「GX産業立地」政策です。脱炭素の地域偏在性や、GX戦略特区制度なども活かした施策、たとえばコンビナート跡地の再生、データセンターの地域分散化・大規模集積化、産業団地等の活用といった、DXとGXを組み合わせた新たな取り組みにも目を向けてみましょう。
GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産が推進する産業まちづくりプロジェクト「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体に先進的なDX基盤整備を行う構想のある新しい産業団地です。超高速通信や自動運転などの最先端技術を取り入れることで、参画する多様な産業のデジタル化を力強く支援します。工業用地の導入を検討されている企業様や、GX・DXなど次世代の経営テーマに関心をお持ちのご担当者様は、GREEN CROSS PARKが実現する産業振興と地域共創にぜひご注目ください。


