私たちの生活の基盤となる住宅そのものがエネルギーを創り、蓄え、地域と連携して機能する――そんな次世代の居住モデルとして注目されているのが、「GX志向型住宅」です。
GX志向型住宅によって、住宅を「生活する場」にとどまらず「企業・地域・産業・環境課題が互いに結びつく住工融合型インフラ」として活用することで、企業の住宅戦略がそのままエネルギー戦略や地域戦略と直結します。今回は、「GX志向型住宅」とは何か、何故企業経営の視点から注目されているのかを整理し、技術や仕組み、政策や諸制度を解説します。
GX志向型住宅の定義

「GX志向型住宅」とは、住宅を通じてGX(グリーントランスフォーメーション)※1を実現するための性能を備えた、次世代型の住宅モデルであり、従来の省エネ住宅をよりも高い水準のエネルギー性能基準を備える住宅のことです。
環境省『子育てグリーン住宅支援事業』における「GX志向型住宅」の要件および補助要件では、以下が明記されています。
- 断熱等性能等級「6以上」
- 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量※2の削減率「35%以上」
- 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」(寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可。都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEHOriented)も可。共同住宅は、別途階数ごとに設定。)
- 高度エネルギーマネジメントの導入(補助要件)
GX志向型住宅は、このように、長期優良住宅※3やZEH※4基準住宅により、さらに高いレベルの性能基準を目指した住宅として制度化されており、高い省エネ性能を持つこうした住宅の運用・活用が大きく期待されています。
※1 GX(グリーントランスフォーメーション ):産業革命以降続いてきた化石燃料依存の経済・社会・産業構造を、クリーンエネルギーを中心とした仕組みに転換し、エネルギーの安定供給・経済成長・温室効果ガスの削減を同時に実現することで、経済社会全体の変革を目指す施策のこと。
※2 一次エネルギー消費量:石油・石炭・天然ガスといった原エネルギーに換算した総量
※3 長期優良住宅:国が定める基準に基づき、耐震性・省エネルギー性・維持管理の容易性などに優れ、長期にわたり良好な状態で使用できると認定された住宅。
※4 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):省エネルギー化や自家発電などにより、1年間に消費するエネルギー量の合計を実質的にゼロ以下に抑えることを目指した住宅。
GX志向型住宅の特徴4つ
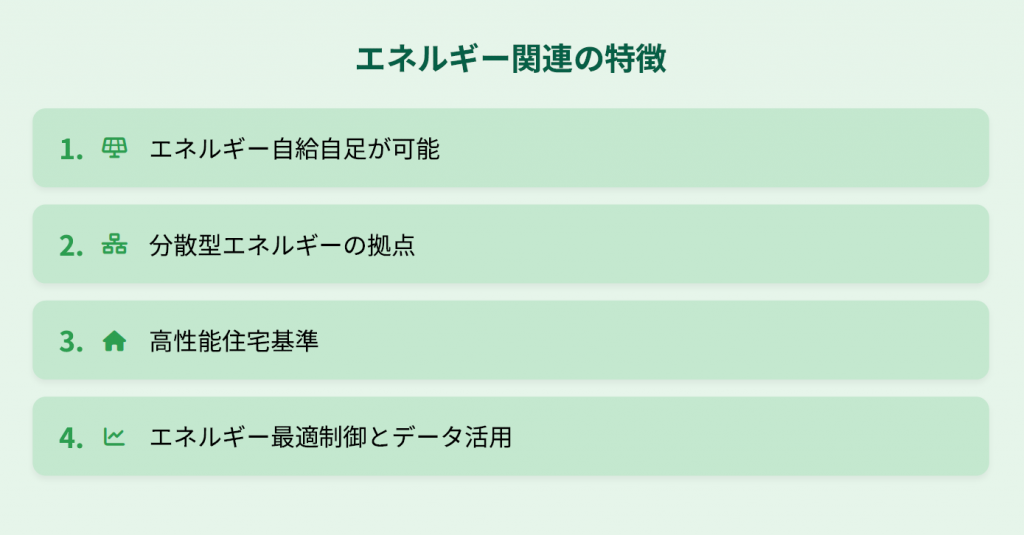
GX志向型住宅は、エネルギー効率化や脱炭素化に向けた社会的な活用が期待される、高いエネルギー性能を持った次世代型住宅です。具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
1. 再エネ電力によるエネルギー自給自足が可能
GX志向型住宅の大きな特徴の一つは、再生可能エネルギーによる電力を住宅自体で創り活用するなど、住宅単位でのエネルギーの自給自足が可能である点です。
例えば、制度上の「再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率100%以上」という要件を満たすことによって、年間を通じてエネルギー収支が0以上、要するに年間で消費するエネルギー以上の量を創出・蓄積できる設計になります。
こうした特徴は、光熱費の削減につながるのみならず、停電・災害など非常時におけるレジリエンス(適応・回復力)の観点で、企業からみても大きな魅力です。
2.地域インフラと連携する“分散型エネルギー”の拠点となり得る
GX志向型住宅は、地域のエネルギーインフラと連携する分散型エネルギーの拠点として機能する点が注目されています。
再エネ大量導入に向かう現代においては、エネルギーの自家消費のみならず、地域全体で消費する分散型エネルギー活用の必要性が叫ばれています。住宅がエネルギーを自給自足するのみならず、余剰電力を地域へ供給したり、または産業施設や物流拠点との電力の融通を行なったりすることにより、GX志向型住宅の性能を最大限活用した地域全体のエネルギーマネジメントが期待できるのです。
住宅が単なる居住空間を超え、地域インフラとして地域全体で連携し、合理的にエネルギーを回していける拠点となることで、GXの地域偏在性の課題やデータセンターの大規模集約化などにも寄与するでしょう。
3.省エネ・高断熱・高耐震などの高性能住宅基準
GX志向型住宅では、制度上の基準が厳しい故に、設備・断熱性・耐震性などの従来住宅に求められてきた性能も向上しています。
例えば、「断熱等性能等級6以上」という基準は、従来の長期優良住宅やZEHなどを上回るレベルです。これは、住宅用途を超えた用途が期待されるGX志向型住宅が、居住環境の快適性を維持しながら、冷暖房負荷の低減や健康性、コストの削減といった、合理的かつ過ごしやすい住宅という居住用途においても素晴らしい特徴を持っていることを意味します。
4.IoT化によるエネルギー最適制御とデータ活用
GX志向型住宅では、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)※5 やBEMS(建築物エネルギーマネジメントシステム)※6、IoTやAIなどを活用して、住宅内のエネルギーの可視化と最適な制御を行ういわゆる「スマートホーム機能」を活用できる点も見逃せない特徴です。
住宅建物内の発電・蓄電量および電力消費量の「見える化」や、インターネットとの連携によるスマートフォン等デバイスでの遠隔制御、IoTセンサーとの連携による室温や湿度の自動調整、AIとの連携によるエネルギー消費の効率化などの最先端技術によって、住宅建物でのエネルギー効率の最大化が期待できます。
また、IoTデバイスを介した確実性の高いデータ収集・データ活用が可能な点も見逃せません。住宅そのものをデータインフラとしても活用することで、GX志向型住宅による新たな価値創出の可能性も出てくるでしょう。
※5 HEMS(Home Energy Management System):家庭内のエネルギー使用状況を専用モニターやパソコン、スマートフォンなどで可視化し、快適な生活環境の維持と省エネルギーの実現を支援するシステム
※6 BEMS(Building Energy Management System):建築物のエネルギー使用状況の「見える化」による意識改革や、設備の更新による効率向上、運用方法の改善などを促進するシステム。
GX志向型住宅を支える技術と仕組み

GX志向型住宅は、「次世代型住宅」と呼ばれるのに相応しい、さまざまな最先端技術が導入・活用されています。ここでは、GX志向型住宅を支える最先端技術や、次世代型の設計について解説していきます。
再生可能エネルギー技術の進化
近年、居住用途の一般的な住宅においても、再生可能エネルギーを活用する技術が多様化・高度化しています。代表的な最先端の再生可能エネルギー技術の例としては、以下の通りです。
- 太陽光発電システム:屋根やカーポートなどに太陽光発電パネルを設置し、住宅自体が電力を生み出す仕組みを作る。さらに、高効率な蓄電池と組み合わせることによって発電した電力を効率的に活用でき、住宅内での電力の完全な自給自足も期待できる。
- 地中熱ヒートポンプシステム:地中熱(深さ10m程度の地中温度)と住宅の熱を交換することによって、季節を問わず常に一定である地中熱(夏は気温より低く、冬は気温より高い)を利用した温度管理が可能になるシステム。地中熱を適切に利用することによって、冷暖房負荷を軽減することが可能になる。
- 風力・バイオマス発電(地域利用型):風力発電やバイオマス(生物由来の再生可能資源)発電などは、住宅単体での活用は難しいですが、地域活用を目的として住宅団地や地域と連携して導入されるケースが増えています。例えば、木質バイオマス発電所や、洋上風力発電施設などで活用されている、地域活用が可能な技術です。 こうした技術をGX志向型住宅と連携させることによって、「創出・蓄電・使用」の住宅単位のエネルギーサイクルが可能になり、GX志向型住宅の技術的な土台となります。
GX志向型住宅は、こうした再生可能エネルギー技術と連携して脱炭素化をさらに進めた、高い基準を持つ住宅であり、一般的な省エネ住宅を超えたエネルギー効率を持つ住宅です。新たなエネルギー創出システムを積極的に活用することによって、より環境負荷のかからない、住宅単位での自立的なエネルギー運用が可能となります。
スマートグリッドによる電力・データ連携
「スマートグリッド」とは、日本では「次世代送配電網」を指します。これは、情報通信技術(ICT)を活用することで、需要側と供給側の双方から相互に連携し、あらゆる電源からの電力の流れを監視・制御し最適化することができる、次世代型の電力網のことです。
スマートグリッドを活用することで、住宅・事業所・地域が互いに繋がったエネルギーインフラを構築できます。具体的には、住宅内のHEMSや建物・工場等のBEMSを地域の配電・蓄電・再エネ設備と統合することで、ICTや制御システムを通じて、電力需給を地域レベルで可視化・最適化します。
このようなスマートグリッドを前提とした地域連携・データ連携環境の中にGX志向型住宅を配置することにより、GX志向型住宅が単なる「住宅内でのエネルギー自給自足」にとどまらず、地域レベルで連携したエネルギーシステムの中の制御機能になります。
カーボンクレジットとトレーサビリティ
GXの取り組みを外部に発信したり、取引先と連携していく上で重要になるのが、GX志向型住宅を通じた「再エネ創出・排出削減量の可視化」と「環境価値(クレジット)の活用」です。
具体的には、住宅における太陽光発電や蓄電池の導入によって創出される再生可能エネルギーやCO2を測定・可視化し、そのデータをJ-クレジット制度のような国内の制度を通じて「環境価値=クレジット」として認証・取引することが可能になります。
これにより、CO2削減実績をトレーサブルに(追跡可能な状態で)管理でき、企業は自社保有住宅や社宅・工場などでのGXで得られたデータを、ESG※7報告やTCFD開示※8の根拠として活用できます。住宅を活用したこうした環境価値の制度的運用は、企業の社会的信頼性やブランド価値、地域との共創価値を高める有効なアプローチのひとつです。
※7 ESG:「環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を踏まえた投資や経営・事業運営」
※8 TCFD開示:気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に基づく、企業による気候関連情報の開示
地域マイクログリッドの活用
地域マイクログリッドとは、「平時には、地域の再生エネルギー電源を最大限活用しつつ電力会社等の送配電網と繋がっているが、災害等による非常時・大規模停電時には、復旧の手段として送配電網と切り離されても、地域レベルで自立的に電力を供給できる」エネルギーシステムのことです。
地域マイクログリッドによって、住宅エリア・産業拠点・公共施設など地域全体が、再生可能エネルギー発電や蓄電設備を共有できます。地域レベルで電力を融通・最適化することで、エネルギーの地産地消(による地域活性化やエネルギー効率化)とレジリエンスの強化を同時に実現できるのです。
「GX志向型住宅」が注目される背景

脱炭素社会を目指す取り組みであるGXの中でも、「GX志向型住宅」が何故今注目されているのかを解説します。
官民連携でGXが推進されている
政府は、ロシア・ウクライナ戦争など国際情勢が緊迫化する中、我が国の安定したエネルギー供給確保と経済成長を目指すため、省エネや再エネ・原子力エネルギーの活用など脱炭素電源への転換や活用(GX)、またカーボンニュートラルに向けた大胆な投資を明言しました。
こうした目標の実現に向けて、政府は「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定。2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップを策定するとともに、目標実現と課題解決に向けた官民連携での様々な取り組みを実行・推進・支援しています。
住宅や建築物に関しては、政府目標として ”2030年度以降新築される住宅について、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す” と設定するなど、住宅・建築物の省エネルギー化の方向を明示しています。
引用:資源エネルギー庁/経済産業省 『ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅』
また、法制度設計の面では、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(いわゆる「建築物省エネ法」)」が改正され、住宅含む全建築物の省エネ性能適合義務の強化を段階的に実施。
こうした背景の中で、産業・住宅・都市インフラの一体化と脱炭素エネルギーへの転換を組み合わせた官民連携の枠組みが年々強化されています。住宅においても、従来のような単なる居住用途のみならず、地域や産業に根ざすエネルギーインフラとしての役割をも期待されているのです。
参考:経済産業省『「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました』
GXは産業構造・生活構造の両面から進んでいる
昨今、企業経営においても「環境・社会・ガバナンス(ESG)」の観点が重要視される状況となっているように、GXは従来、エネルギーインフラや物流の問題といった産業構造の変化に注目が集まっていました。しかし現在では、住まいや都市インフラといった、暮らしそのものにも大きく関係してきています。
例えば、「建築物エネルギー消費性能誘導基準」をZEH・ZEB※9水準の省エネ性能へと引き上げる方針が策定され、ZEH・ZEBなど高い省エネ性能を備え、エネルギーを生み出す建築物の普及が進んでいます。住宅自体が「消費」主体から「創出・蓄積・制御」主体へと転換されるという、産業構造・生活構造の変化が進んでいるのです。
※9 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル):省エネルギー対策や自家発電などの取り組みにより、年間のエネルギー消費量を大幅に抑えた建築物。
参考:国土交通省 『住宅・建築物の省エネルギー対策に係る最近の動向について』
新たなGX基盤としてGX志向型住宅が期待されている
こうした流れの中、従来の省エネ住宅・長期優良住宅・ZEHをさらに超える省エネ性能基準を持つ住宅モデルが策定され、期待を集めています。
環境省が主導する脱炭素志向型住宅の導入支援事業(子育てグリーン住宅支援事業・2025年度)において、「GX志向型住宅(GX-oriented housing)」が次世代住宅として定義され、高い省エネ性能を持つ住宅モデルとして注目されました。
GX志向型住宅の性能基準は、2025年度の補助金制度終了後も、 企業が目指すべき次世代住宅の指標として有効であり、 社宅・従業員住宅・住宅開発プロジェクトなど、企業経営における 住宅戦略の重要な基準となっています。
注)2025年度の子育てグリーン住宅支援事業(GX志向型住宅)は、 予算上限到達により2025年7月に申請受付を終了しています。 2026年度以降の支援制度については、環境省・国土交通省の公式サイトで 最新情報をご確認ください。
企業のGX志向型住宅導入で生まれる価値

企業がGX志向型住宅を導入・活用することで、住宅や建築分野をGX戦略の一環として取り込み、新たな企業価値が生まれます。具体的にどのような価値が生まれるのかを解説していきます。
GXを「競争戦略」として実施
「GXは競争戦略」と捉える視点が大切です。例えば、社宅をGX志向型住宅として整備することで、従業員への福利厚生・住宅コストの削減・企業ブランド価値の向上・エネルギー自給によるレジリエンス強化というように、競争戦略としても多角的な効果が期待できます。
地域と共に成長・環境貢献する“共創型企業像”の形成
GX志向型住宅の導入や活用、あるいはその支援といった取り組みを行うことで、地域全体でのエネルギー循環、災害時のレジリエンスを含めた、住居インフラや地域環境の質の向上に貢献できます。
また、こうしたGXの取り組みを通して、自治体や住宅事業者、デベロッパー等との連携体制を構築することで、地域共生・共創型企業としてのブランド化も目指せます。GXを企業単位ではなく地域単位で協力して行うことで、単なる企業活動にとどまらない社会貢献・環境貢献活動へ広げていくことにつながるのです。
たとえば、地域の再生可能エネルギー発電機能と蓄電設備、産業団地や住宅団地を連携させたGXを前提とした住宅開発は、地域再生・企業ブランド・エネルギー戦略を設計段階から一体化する絶好の機会です。
人材確保と定着を支える新たな福利厚生
GX志向型住宅の活用は、優秀な人材確保、人材定着につながる競争価値をももたらします。
売り手市場の中、優秀な人材の確保のためには、魅力的な福利厚生が欠かせません。GX志向型住宅を従業員向けの社宅として整備することは、優秀な次世代人材、特にサステナビリティ志向の若年層の採用や定着につながるでしょう。彼らにとって、高断熱・高効率かつ低コストで快適性の高い省エネ住宅という福利厚生は、他社との大きな差別化になり得ます。
GX志向型住宅を従業員に提供すれば、働き方改革やウェルビーイング経営とも連動し、企業の組織としての魅力が大幅にアップするでしょう。
GXを軸とした投資と成長に期待できる
GX志向型住宅の活用から住宅開発・再エネ導入・地域連携へと視野を広げていくことで、より大きな資金調達への期待が生まれ、さらなる投資が可能になることで持続的な企業ブランド価値の強化にもつながるからです。
こうした好循環を生むことで、住宅を単なる資産ではなく、地域・産業と密接に連携する「戦略的資産」へと転換でき、戦略的資産の活用によって、企業は持続的成長と価値創出を見込めるでしょう。
まとめ:GX志向型住宅が描く未来

GX志向型住宅は、単なる1つの住宅の域を超えた、脱炭素社会の新たな都市インフラとなり得る可能性を秘めています。企業・自治体・地域住民が「共に連携し、共に創る」GX型のコミュニティの基盤ともなり得る存在です。
GX志向型住宅を通じて、再生可能エネルギーを創り、エネルギーを効率的に制御し、地域と共生する。これこそが、GX志向型住宅が描く「住×産業」の未来戦略です。社宅や地域住宅、産業施設等をGX志向型モデルへ変えていくことによって、脱炭素化と人材戦略に加え、企業ブランド価値・地域価値を同時に高めることが期待できます。GXインフラを前提とした先進的な経営判断として、GX時代に即した住宅インフラを設計・活用しましょう。
GREEN CROSS PARKのGX

東急不動産が推進するプロジェクト「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、環境負荷低減と産業発展の調和を目指す産業まちづくり事業です。
エリア内では、クリーンエネルギーの導入や炭素排出量の適切な管理を通じて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。多様な企業がこの場所に集い、互いの強みを掛け合わせることで、GXのさらなる加速を図ります。
東急不動産は、持続可能な未来の実現に向けて、GREEN CROSS PARK事業を積極的に展開しています。


